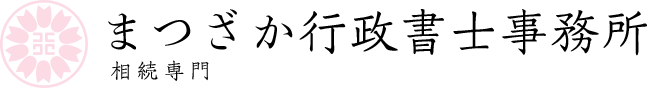相続や遺言書作成はまつざか行政書士事務所にお任せください
INHERITANCE
まつざか行政書士事務所は、遺言書作成・遺産分割から相続税申告、終活サポートまであらゆる手続きをワンストップで対応します。宮城県仙台市に根ざし、地元ならではの知識を活かしながらお客様一人ひとりに最適な解決策を提案。女性 行政書士として、配偶者の介護、子供の教育費など、女性特有の悩みにも寄り添います。また、当事務所は不動産会社も併設しており、不動産問題もまとめて解決いたします。
相続とは?
INHERITANCE
親しい親族が亡くなり、あなたに遺産を残していたとしましょう。その遺産を受け取ることが「相続」です。相続する際は、その遺産に対して「相続税」がかかるため、手続きなど難しいイメージを持たれる方もいらっしゃるでしょう。実際、いざ相続となると慌てる方が少なくありません。急な相続で混乱しないため、損をしないためにはあらかじめ基礎知識を身につけ、対策をしておくことが重要になるでしょう。
相続をする方(被相続人)への対策
INHERITANCE
相続問題においては、「心の準備ができていない」「手続きが多くて大変」と悩む方が数多くいます。ですが、一般的に相続する側(被相続人)が亡くなった後にできる相続対策はほとんどありません。万が一のときに慌てないためには、被相続人が健康なうちから対策を行うことが重要です。たとえば相続人が元気なときや、認知症を発症する前に対策を講じておけば、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などが可能に。成年後見制度である「任意後見」を利用すれば、信頼できる家族の中から後見人を選出することもできるでしょう。これにより、効果的な相続税対策を実現できるはずです。
相続を受ける方(相続人)への対策
INHERITANCE
相続人同士のトラブルは、仲の良い家族や親族との間でも起こりえます。遺産分割協議をまとめても、修復不可能なほどの亀裂が発生することも。相続について早めに話し合い、無用なトラブルを避けるようにしましょう。
相続発生後に有効な対策としては、相続税の節税が挙げられます。相続財産の評価額を引き下げる、各種控除を適用させるなどの方法があるでしょう。相続した不動産を売却するとなったら、名義変更を行う必要も生じます。相続登記時には相続人全員で話し合う必要があり、相続人を単独名義・共同名義のどちらにするかなどを決めます。実は、この名義変更は相続時に「揉めやすいポイント」です。できる限り穏便に話し合いを進めるためにも、前もって相続人全員で協議しておくなど、対策が必要になるでしょう。
遺産相続
INHERITANCE
相続を進める際、分配方法などの意思決定をするときは相続人全員の合意が必要になります。遺産分割協議を開き、法定相続人全員で財産の分け方などを決めることになるでしょう。最終的には、協議に関する全員の合意の証明として、「遺産分割協議書」という書類を作成します。ただし、ここに至るまでに「どのように遺産を分割するのか」という問題に直面するでしょう。ここでは、主な分割方法について紹介します。
現物分割
たとえばあなたの父親が亡くなり、遺産として自宅と預貯金、現金を残してくれたとしましょう。この場合に「自宅は妻へ」「預貯金は長男へ」「現金は次男へ」というように、全員がそれぞれの遺産を分割して受け取ることを「現物分割(げんぶつぶんかつ)」と呼びます。
換価分割
不動産や株券などが遺産として残されるケースもあります。これらは簡単に分割することが難しいため、その価値を評価してもらった上で売却し、一度現金化した後で全員に分割する方法があります。これが、「換価分割(かんかぶんかつ)」です。ただし、不動産が遺産として残されていた場合、すぐに売却できるとは限りません。交渉や手続きを円滑に進めるためにも、事前に信頼のおける不動産業者などに相談しておくことをおすすめします。
代償分割
たとえば、親族の遺産が自宅のみで、相続人はあなた(長男)と弟(次男)だけだったとしましょう。「代償分割(だいしょうぶんかつ)」とは、まずは長男であるあなたが唯一の遺産である自宅を相続し、その代わりに次男である弟に「代償金800万円を支払う」という方法です。
共有分割
親族の遺産が自宅のみで、相続人は母親(妻)とあなた(子)の2人だけだったとしましょう。この自宅を母親とあなたで2分の1ずつ相続し、全員(2人)で共有する分割方法を「共有分割(きょうゆうぶんかつ)」と呼びます。
相続したくないとき
INHERITANCE
管理に手間がかかる古い建物や、固定資産税の支払いが負担となる土地、莫大なローン残債など、「相続したくない」財産も少なくないはずです。相続したくないときは、相続放棄や限定承認などの手続きを取れます。
単純承認
被相続人が残した財産のすべての権利と義務を、相続人が共同で引き継ぐ方法です。マイナス財産がプラスの財産より多い場合は、相続人が自分の財産から弁済しなくてはなりません。被相続人の財産を勝手に処分すると「単純承認を受け入れた」と判断され、相続放棄できなくなるので注意しましょう。相続を知って3ヶ月間、とくに手続きをしなければ単純承認したと見なされます。
相続放棄
プラスの財産もマイナスも財産も一切放棄し、相続人の立場を辞退する方法を指します。相続放棄は相続人一人の判断で決定できます。一度選択すると、最初から相続人でなかったと見なされます。相続放棄を希望する場合は家庭裁判所に、相続開始後3ヶ月以内に申し立てましょう。なお、相続放棄は撤回できません。
限定承認
引き継いだ債務を、引き継いだプラスの財産の範囲内で返済するのが限定承認です。この方法を取る場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。債務の弁済に自分の財産を使う必要はありません。債務を返済した後に遺産が残ったらそれを相続できます。そのためには、相続人全員の同意や裁判所への申し立てが必要になる点には注意しましょう。なお、この方法は税金面で不利になることもあるため、実際にはあまり行われていないようです。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。 正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
>>詳しくはこちらから
遺言書
INHERITANCE
遺書とは「自分の死後のために書き残された手紙」です。一方遺言書は、遺産を残す人(被相続人)が自分の亡くなった後のことを考え、遺産の分配方法などを生前に準備しておくもので、法的な効力を持つ書類を指します。思いついたことをただ紙に書き残すのではなく、決められた形式にしたがい記述・署名・捺印を行う必要があります。遺言書に不備があると効力が無効になることも。そうならないためには専門家にアドバイスをもらい、確実に実行される遺言書を用意する必要があるでしょう。ここでは、遺言書の種類を紹介します。どの遺言書が最適か判断するのにお役立てください。
自筆証書
自筆の遺言書を指します。簡単に作成できる一方、莫大な遺産がある場合は不安が残る方法です。なお、この場合も最低限の証明手続きは必要になります。確実に故人が書いたものであることを家庭裁判所に認定してもらう、「検認」が求められる点は注意しましょう。
公正証書
一番認知度が高い形式の遺言書です。国の役所である「公証役場」で作成され、その内容には必ず公証人と呼ばれる人のチェックが入ります。そのため、ほぼ確実に法的効力を持つ遺言書を作成できるでしょう。家庭裁判所の検認も不要で、相続が発生した時点から効力が発生するのも特徴です。ただし、手続きの煩雑さと作成にかかる費用などはデメリットと言えるでしょう。公証人や立会人などに支払う費用なども発生する点は注意が必要です。
秘密証書
内容を誰にも知らせることなく、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらうのが秘密証書です。遺言書の内容を、誰にも見せたくない場合は有効な手段でしょう。ですが、機密性を意識し過ぎた結果、遺言書自体が無効になるリスクがあるため、現在ではあまり採用されることはありません。
特別方式
ここまで紹介した「普通方式」と呼ばれる一般的な形式とは異なり、「特別方式」と呼ばれるタイプもあります。これは、いわば「緊急時の遺言書」です。ゆっくりと時間をかけて普通方式の遺言書を用意することが難しいとき、複数人の立会人を交え急いで作成する遺言書がこれに該当します。口頭や代筆も認められるのが特徴です。この方法を採用するケースは稀ですが、万が一の場合でも遺言書は作れるのだと覚えておくと良いでしょう。
家族信託と成年後見制度
INHERITANCE
家族信託と成年後見制度の違い・比較
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 家族信託 | 任意後見人 | 法定後見人 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 受託者(家族や親族)として財産の管理・運用・処分を行う | 判断能力が低下したときに備え任意後見人と契約締結しておき、財産管理や身上管理を代行してもらう | 判断能力が低下した人を守るため法定後見人に財産管理や身上管理を依頼する |
| 財産管理者 | 受託者 ※信頼できる人への依頼ができる。 |
判断能力があるうちに指名し、契約した任意後見人 | 裁判所が専任した法定後見人 ※司法書士や弁護士等の専門家が選出されるケースも。 |
| 対策できる時期 | 判断能力が低下する前 ※判断能力が低下していても状況によりで対策できることも。 |
判断能力が低下する前 ※判断能力が低下していても状況によりで対策できることも。 |
判断能力が低下してからのみ可能 |
| 開始時期 | 信託契約締結時 | 判断能力が著しく低下し、家族や親族が家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任されたとき | 判断能力が低下し、家族などの申し立てにより成年後見人が専任されたとき |
| 不動産の処分 | 信託契約内容の範囲内での管理・処分できる | 合理的理由が認められると、家庭裁判所や後見監督人の同意なしに処分できる | 居住宅の売却は家庭裁判所の許可が必要。合理的な理由により許可される |
| 監督機関 | 信託監督人や受益者代理人を信託契約で定めることが可能 | 家庭裁判所で専任された任意後見監督人 ※司法書士や弁護士等の専門家と家庭裁判所。 |
司法書士や弁護士等の専門家が成年後見人に専任されるケースも |
| 初期費用 | 専門家への相談料(信託財産の1%程度) ※そのほか公正証書作成費用なども発生。 |
10~20万円程度 ※司法書士へ手続きを依頼した場合。 |
10~20万円程度 ※司法書士へ手続き依頼した場合。 |
| 月額費用 | 原則なし | 任意後見人への報酬が発生 月額0~5万円 ※親族などの場合。 月額3~6万円 ※専門家などの場合。 |
居住宅の売却は家庭裁判所の許可が必要。合理的な理由により許可される |
家族信託と成年後見制度を適正に活用する判断基準
1.本人が自身の財産管理に不安を覚えていないか
高齢のご本人が不安を感じている場合は、家族信託の利用を検討しましょう。今後の財産管理について、誰に任せていくか、どのように管理していくかを本人の意思で決定できます。財産管理に加え将来の生活についても不安がある場合には、任意後見制度を併用する方法も。なお、ご本人が将来の生活についてのみ不安を覚えているなら、任意後見制度の活用を検討しましょう。
2.本人が認知症などで意思能力を失ってしまっていないか
意思能力を失っている場合、契約行為である家族信託や任意後見は利用できません。この場合、成年後見制度の利用しかできなくなります。そうなる前に、家族信託や意後見制度の利用について、検討するようにしましょう。
行政書士ができること
INHERITANCE
相続手続きは、相続人の方々が自力で行えます。ただし、相続関連の手続きは複雑な内容が多く、さまざまな書類を取り寄せる必要も。行政書士にはそうした面倒な手続きを丸投げできるので、相続人の負担を軽減できます。書類作成や手続きも不備なく進められるでしょう。なお、行政書士への依頼は、弁護士などのほかの士業と比べリーズナブルです。
まつざか行政書士事務所として
INHERITANCE
相続や遺言は、人生において何度も経験するものではありません。分からないこと、不安なことがたくさんあるのは当然でしょう。まつざか行政書士事務所は、皆様の人生における大切な節目を、親身になってサポートする地域密着型の行政書士事務所です。